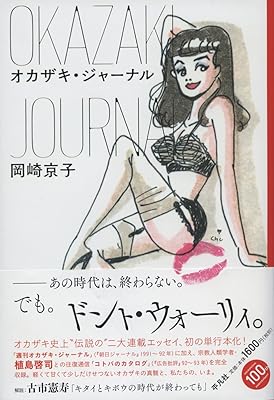NYでの日々
2025年12月27日
ずいぶん昔のことになるが、世界的に有名な美術家の河原温(かわら・おん)さんと渋谷でマージャンをやったことがある。メンバーは、河原温さん、北島敬三さん(写真家)、パルコのメンバー、そして、ぼくという4人で、河原さんは飄々とした風情でマージャンを楽しんでいた。北島さんはものすごく念を込めて牌を引いていて、牌が手の汗でくっついてしまうほど気合いが入っていた。ぼくがそれを笑うと照れ臭そうにしていた。外見はちょっと怖そうだがとても愛すべき人物だった。
その後、ぼくがNYの大学で教えることになりダウンタウンに移ってからも、河原温さんの自宅でマージャンをやったことがある。壁には河原さんの作品(「APR.24,1987」とか言うように、何の変哲もない日付が描かれた絵画)が並んでいる。河原温さんが世界的に有名なコンセプチュアル・アートの第一人者としてすでに知らぬものがないほど有名であることをその頃には薄々気がついていたが、そんなこと抜きにただひたすらマージャンをやるのが楽しいとぼくは思っていた。河原温さんの個展には絶対に本人が現れないのでNYでも「インヴィジブル・アーティスト」(見えないアーティスト)と呼ばれていたが、ぼくはそんな河原さんがマージャンのたびにケータリングで食事を用意してくれるのをありがたく頂戴していた。
後輩で仲良しの四方田犬彦が書いた『ストレンジャー・ザン・ニューヨーク』(朝日新聞社)のおかげでいろいろな人(主にダンサーたち)とも知り合いになれたし、なんといっても作家の佐藤紘彰さんにはとてもお世話になった。コロンビア大学の俳句の会にゲストで呼ばれて、大勢のアメリカ人たちの前で代表的な俳句を読んでくださいと言われ大汗をかいたのもいい思い出だ。いま思い出しても楽しいことしか思いだせない。
それに対して、河原温さんとよく並び称される、やはりこちらもNY在住の世界的なアーティスト荒川修作さんとは日本の雑誌『流行通信』で対談して以来けっこう親しい仲になっていた。その『流行通信』の編集長だった大竹秀子さんはぼくの東大時代のクラスメートで、大学に入って最初にデートした間柄でもあった。彼女もその時はすでにNY特派員としてぼくのアパートから15分くらいのところに住んでいた。そこはインド人街と呼ばれる一角で、ある日の午前中にその近くのスーパーに入ってすぐに店のなかでバッタリ出会ったことがあった。「あっ、大竹さん」というまもなく、彼女はその姿を消していた。一瞬の出来事だった。それもそのはず、そんな時間にスーパーにいるのにぴったりの服装で、しかもノーメイクだったからだ。彼女とは詩の朗読会とかでも会ったことがあるし、もっと親しくランチでもしたらよかったのにと思ったものだった。
荒川修作さんとの対談は抱腹絶倒だった。なんともいえない「オー、イエーイ」とか妙な英語の合いの手がときどき入る。夕方に始まった対談が夜の8時ごろになってそろそろ終わりに近づいたかなと思っていると、荒川さんは、突然、「今日はこれでお互いが何を考えているのかよくわかった。で、続きはどうするか」と言い出したのだった。それまでほとんど荒川さんの独壇場で、ぼくはひたすら合槌を打つばかりだったのに、そんなことわれ関せずといった様子だった。荒川さんとはそれからも日本のテレビで1時間30分の特別番組を作ってみたり、荒川さんを信奉するアニメーション映画監督の宮崎駿さんとの対談の司会をやったり、岐阜県養老町に彼がつくった「養老天命反転地」(テーマパーク)をめぐったりして、その後も長く交流は続くのだった。
アメリカに長く住む日本人アーティスト同士はだいたい不仲と聞いていたので、決して相手の名前をこちらから出したりしないで、楽しいことだけ共有していこうと思っていた。NYでは多くのアーティストと交流していた。偶然だったが、坂本龍一さんの奥さんともちょっとヘンなところでしばらく一緒だった。ずっと後になって、仲が良かった細野晴臣さんのステージを見に行った時に坂本龍一さんに「NYでは彼女と一緒だった」と言ったら、「彼女からよく聞いています」と言っていた。なつかしい思い出だ。ぼくのアパートはおんぼろながら住めば都でとても気に入っていた。トイレには鍵がかからないし、なんと部屋に入ったすぐ横にバスタブがむき出しで置かれていて、遊びにきた女の子たちはみんな恥ずかしそうに入浴していた。誰かが入っているときは見ないことになっているのだが、狭いアパートなのでどうしても視界に入ってしまう。みんなでげらげら笑いながら楽しい時を過ごすのだった。
そんなアパートだったが、NYはまだましなほうで、20代のころ住んだシカゴのアパートでは強盗団が1階に潜んでいて、早朝に突撃した警官隊と乱闘になったり、ぼくの部屋の上の階に住んでいたゲイのカップルがよく大げんかして大変な騒ぎになったりしていたのだった。それに比べれば、ニューヨークで一番治安が悪いと言われていた地区(トンプキンス・スクエア・パーク近辺)ではあったが、大過なく過ごせたことはありがたいと思わなくてはならないだろう。
人生の大半を旅で過ごし、世界中の国々を訪れたこともあったが、これからも海外に行くことができるだろうか。身体も悪くして、もうそんなこともできないだろうが、それでも記憶のなかでは夢幻のなかで過ごした日々がいつでも甦ってくるのだった。
keiji ueshima